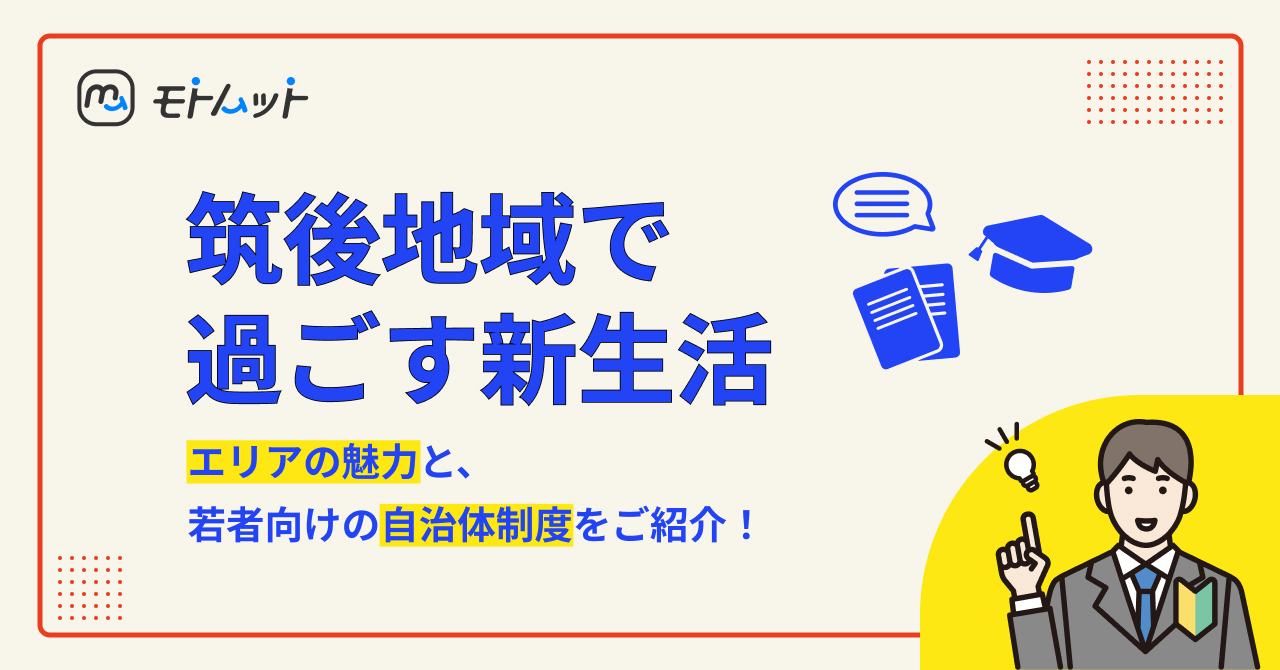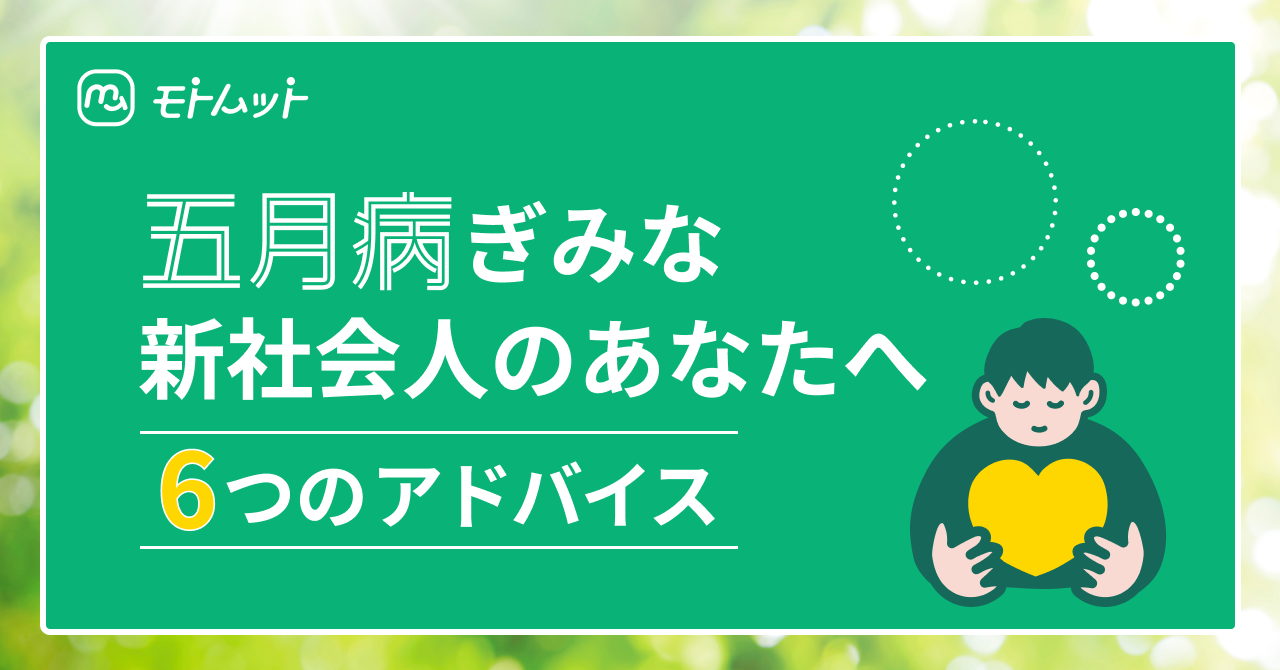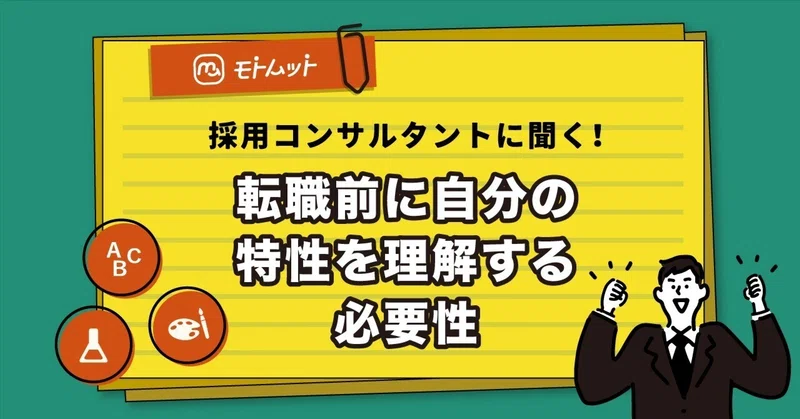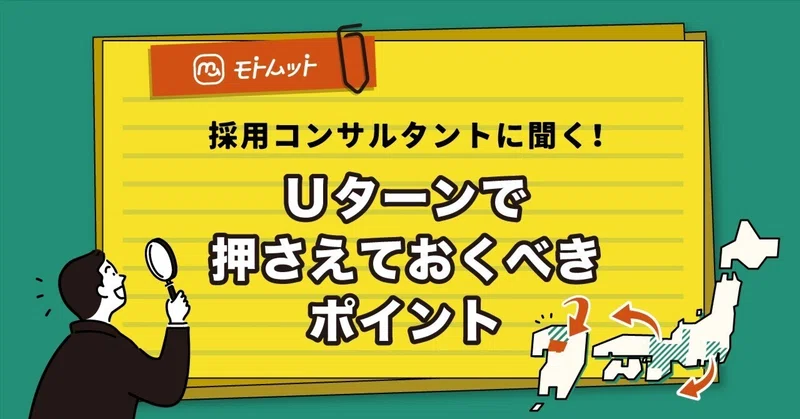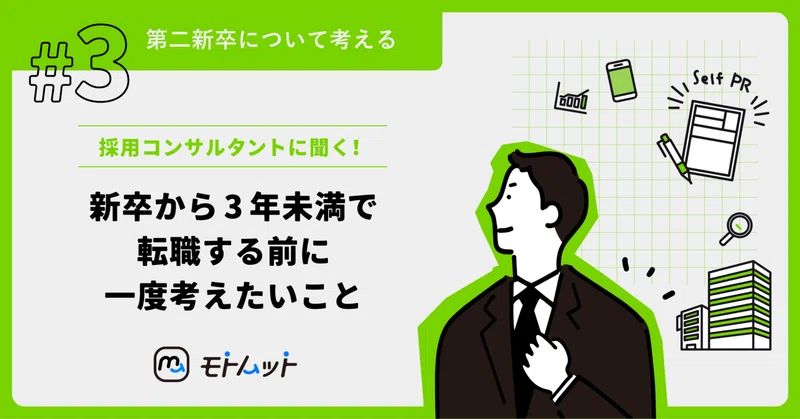モトムットは、筑後地域の企業の様々な挑戦を応援しています。
今回、特集でご紹介するのは株式会社六花(八女市)。
日本の古い家屋が抱える課題を解決しようと高品質な家づくりに取り組み、地元で支持を得ています。
代表者への動画インタビューも交えながら、その想いをお伝えします。
冬はヒートショック、夏は熱中症・・・
年間1万7,000人。
この国において「ヒートショック」に関連して入浴中に急死したと推定される人の数だ。
ある医療機関が2011年に発表した推計値で、交通事故で死亡する人の5倍以上の数だといわれている。
近年、冬になると頻繁にメディアでも取り上げられる「ヒートショック」だが、改めて概要を説明すると・・・

ヒートショックは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度変化により血圧が上下に変動することなどが原因で起こる。
失神や不整脈のほか、死に至ることもある。
高齢化が進み、その数は年々増えているとされ、日本気象協会は「ヒートショック予報」等で日々、注意を呼びかけている。
日本は先進国の中でもヒートショックの発生率が突出して高いといわれているが、そこには古くからある日本の住宅の構造が関係しているという。
福岡県八女市で注文住宅を提供する株式会社六花の代表・石橋和也さんは、次のように話す。
石橋さん
「日本の断熱基準は先進国の中でかなり遅れています。本来、家は安心して住まうものですが、実際のところ、冬にヒートショックになったり夏に熱中症になったりする人が後を絶ちません」

高温多湿な気候のため、古くから「風通しの良い家」を作ってきた日本。
冬場は、居間など長時間過ごすスペースのみが重点的に暖められるため、風呂場や廊下など行き来が少ないゾーンとの温度差が大きくなりやすい傾向がある。
また、日本で「断熱材」が一般的に使われるようになったのは1980年代と、諸外国に比べると遅い。
その後も、断熱性に関する基準の整備はなかなか進まなかったが、ようやく2025年の4月から「省エネ基準の適合」が義務化されることになった。
(これにより、断熱等級4に満たない家は建てられなくなる)
「地域の資産」になるような家を
こうした背景があるなか、六花は会社設立の2016年から「断熱性」と「気密性」にこだわった住まいづくりに取り組んできた。
石橋さん
「以前勤めていた住宅会社では、営業としてお客様に家を販売していました。耐震性や断熱性の基準ができる前だったため、後になって、『夏は暑く、冬は寒い、理想とは逆の』家を売ってしまっていたのではないかという思いを抱きました。この経験から、六花を立ち上げる際には『本当に価値のある家を』という気持ちが固まっていったのだと思います」
六花は会社のパーパスとして「この町に資産を。」という言葉を掲げている。
優れた性能で何代にも渡って住み続けられる家を建て、地域の資産として残していきたいという石橋さんの想いが込められている。


六花では購入の際、断熱性能の最高水準である「断熱等級7」か「断熱等級6」のいずれかを選択してもらう形をとっている。
また、気密性※を表す「C値」も全棟で測定するなど、高いスペックでの提供を約束している。
※空気や気体が漏れない性能、または屋内と屋外との空気の移動による熱の移動を少なくする性能。
石橋さんへのインタビュー動画では、六花が見据える未来や求める人物像について語っていただいた。
▼動画リンク
https://motomutto.jp/front/movies/1114
左官職人の意匠が六花の原点
高性能をとことん追求する六花の志向はどこから来るのか、石橋さんに尋ねてみた。
石橋さん
「実家の会社が左官工事から始まった会社だということです。左官職人は昔から、多岐にわたる材料で施工していました。季節の温湿度まで細かく加味して素材を調合します。また、鏝(コテ)を扱う所作は美しく一目置かれるものでした」
かつての左官職人が取り組んでいたような丁寧な家づくりは、戦後復興期に住宅が量産される過程で次第に薄れていったと石橋さんは指摘する。
世界基準で日本の住宅の在り方が見直され始めた今、六花では脈々と受け継がれてきた“左官マインド”を活かした妥協しない家づくりが強みとなっている。

石橋さん
「コストパフォーマンスの高い世界基準の家をつくり続けます。一方で、そのための技術者が地元に足りていないとも感じています」
【六花が求める人材】
▶︎性能・デザインいずれにも手を抜かない建築士
▶︎工程を丁寧に管理する現場監督
▶︎六花の想いを形にする自社施工職人
石橋さん
「何世代にも渡って暮らせる家がこの地域に増えたら、いつか建て替える人はいなくなると思いますが、その時は住宅ではない別の事業をやります」
「本当に価値のある資産を、この町に残したい」という六花の信念は相当なものだ。
これからも世界基準で求められる性能と地域との融合に徹底的にこだわる。